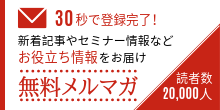コラム
いまさら聞けない、「企業と生物多様性」(その5)-「自然を守れ」が生物多様性保全ではありません本多清のいまさら聞けない、「企業と生物多様性」

前回のコラムでは、地域の自然と、そこに暮らす人々との関わり方(地域固有の文化)を守り育み、あるいは再生していくことが、地域に根ざす企業の生物多様性戦略として重要である旨をご紹介しました。しかし、それをいざ実践しようとすると、いろいろな矛盾点や疑問点が浮かんでくると思います。今回はその具体例のひとつを紹介します。
「地域本来の自然」とは?
地球上の様々な生物を宇宙船の乗組員にたとえた、「宇宙船地球号」という言葉をお聞きになったことがあると思います。これをもう少し具体的にイメージするために、地球上の多様な生きものたちを企業の社員にたとえた「株式会社・地球」を想像してみましょう。
企業の社員を大枠でタイプ分けすると、特定の技術に長け、その技術を活かして企業に貢献する「専門職」と、全体をマネジメントしつつ会社組織を管理運営する「総合職」になると思います。では「株式会社・地球」の場合はどうなるでしょうか。
答えは「総合職なき巨大企業だった」です。地球上の生命(生物種)はすべてが「自らの種(遺伝子)を存続させるための技術に長けた専門職」であり、生存競争の中でひたすら「生きて子孫を残す」ことだけを目標に邁進してきたわけです。その結果、様々な自然環境や気候変動の影響を受けつつも、多くの他種の生物との関係性の中で、それぞれの地域における「生態系」という社会(企業なら「部署」に該当するでしょうか)を構成してきたわけです。
私たち人間も、つい四半世紀前までは地球上でひたすら自らの利益のための営み(生産と消費)に励んできた「専門職」の生物でした。そして、いま現在の私たちは「地球環境をどうしていこうか」という「総合職」的な観点を持たざるをえない状況になっています。これは、ほんの少し前まで、日々の生活を「専門職」として営みながら「生態系」という地域社会(部署)を支えていた生物(人間)が、その活動を通じて生態系との軋轢をおこすに至ってしまったからこそ、必要となったことです。「総合職なき巨大企業だった」と過去形にしたのは、このためです。
もう、あえて説明しなくてもご理解いただいているかと思いますが、生物多様性において守るべき「地域本来の自然」は、私たち人間の営みの影響を除けば再現される、というわけではありません。生態系という「部署」の成立に、人間という「社員」は本来的に欠かせない存在なのです。
地球上で人間の影響をほとんど受けずに成立してきた生態系、いわゆる「手つかずの自然」も、確かに存在します。そのような自然を守るためには、人間を排除し、手つかずの状態を維持することが必要です。しかし、人間生活が営まれている地域の圧倒的大部分は、人の働きかけとの関係の中で自然が維持されています。「人の存在を含めた地域本来の自然」を守る方法は、「手つかずの自然」を守る方法とは明らかに違うのです。
守るべきは「人が築いてきた4次元ワールドの自然」です
もし、いま日本列島から人間が一人もいなくなり、その後200年も経過すれば、生物多様性は「著しく劣化」してしまいます。どのように劣化するかというと、本州の場合はほとんどの陸地は鬱蒼とした常緑樹(暖地性のシイ・カシ類など)の森に覆われ、非常に単一的な環境になってしまいます。いわば神社などの「鎮守の森」が全国に広がった状態になるわけです。そのような環境に適応した生態系こそ成立しますが、それ以外の多様な環境(落葉樹の森や草原、水田等)で成立していた生態系は失われ、そこに住んでいた様々な生きものたちも姿を消していきます。人間がいるからこそ、さまざまな環境が生まれ、そこに暮らす多様な生き物たちが生き延びてきた。それが、日本の自然の特徴なのです。
人間がいなければ、自然は長い時代の気候変動(温暖期や氷河期等)に応じて変化しつつも、単調な環境が広範囲に広がる状態になっていたことでしょう。しかし、例えばそこで人が木を切ると、その環境に変化が起こります。森林が長い時間の中でたどる変化を人の行為がリセットし、切り開かれた森で、また新たな時間が流れ始めます。いわば人間の行動はタイムマシーンのように「様々な時代の生きものが暮らす多様な環境」をモザイク状に生みだしてきたのです。
専門的な言葉では「自然遷移(せんい)への人為的攪乱(かくらん)」と言いますが、こうした人間の営みの影響があったからこそ、「地域の自然」は温暖期や氷河期等の様々な気候変動を経験しながらも、それぞれの時代の生きものたちが生き延びて暮らすことができる「4次元ワールド」としての多様性を築くことができたわけです。これこそが、私たち日本の企業関係者が守るべき「地域本来の自然」の正体であるといってよいでしょう。
「破壊のとき」こそ「再生のチャンス」です
さて、四半世紀前ぐらい前までは華やかだった「自然保護運動」も、最近ではあまり耳にしなくなりました。理由の一つは、公共事業や企業開発による大規模な自然破壊が行われにくい社会情勢になってきたからです。その意味では、日本という国はずいぶん変わりました。もちろん、「よい国」に成熟したわけです。
しかしもう一つの理由は、新たな課題といえます。日本の生物多様性を劣化させている大きな原因として、「人の営みが衰退したこと」が焦点になってきたからです。里山の森の荒廃や、田畑の耕作放棄地の拡大などがそれです。そのような状況の中でも、かつて人が営みと共に育んだ「4次元ワールドの生きものたち」は、けなげに生き残ろうとしています。でも、そろそろ限界が近づいてきているのです。
企業が大規模な工場用地や巨大なショッピングモールを開発しようとする場合、地元の自然保護団体等が開発反対を唱えるかもしれません。しかし生きものたちは、開発さえしなければ末永く守られるのでしょうか? 否、このまま時の流れに任せていては、遅かれ早かれ滅びていく「地域の生きものたち」を救うことはできないのです。
ここに、大いなるチャンスがあります。
開発による破壊の規模が大きいほど、そのようなプロジェクトを実施できる企業は、同時に「大いなる再生のチャンス」を生む力をも備えていることに気がつくべきです。
田園や里山の生きものたちは、かつて人の営みと仲良く暮らしていた存在です。それを脅かしている原因は「人の営みの衰退」にあるのですが、衰退の中身には量的なものと質的なものがあります。「量的な衰退」とは、里山の荒廃や耕作放棄地の拡大を意味します。
もうひとつの「質的な衰退」とは、大量生産・大量消費・大量廃棄の時代が生んだ「多面的な価値や機能の喪失」です。例えば、かつて多くの生きものを育んでいた水田は、「米を安く、簡単に、大量に」生産する単一機能のみが求められ、生産効率性を極大化するための装置に変化しました。その結果、メダカやホタルを育んだ水路はコンクリート製の排水溝となり、農薬や化学肥料が、トンボやカエル等の多くの生きものたちの姿を失わせていきました。
こうして「生産効率の向上」が進めば進むほど、「田園の生産機能」に必要な人手(つまりマンパワーコスト)は少なくなり、「地域の歴史に育まれた様々な生きものたちと人の営みが織りなしていた物語」の担い手も、居場所を失っていったといえます。まさに「近代化が招いた田園のリストラと価値喪失」です。
企業がこのような地域で開発プロジェクトを進めるなら、こうした「失われた価値の物語」を掘り起こし、読み解いて、地域の住民や社員と共に再構築していく「智恵と術」も共に携えて乗り込むべきです。開発の前よりも開発後のほうが生物多様性が豊かになる状態は「ネット・ポジティブ・インパクト」と呼ばれ、開発に携わる企業が生物多様性において目指すべき姿とされています。
「あの会社がやって来たからこそ、この地域の自然と文化がよみがえることができた」と言わしめる巨大開発。それは決して夢物語ではなく、もはや具体的な目標とされているのです。
※本コラムを執筆した本多主任研究員が生物多様性とビジネスチャンスについて寄稿した一般社団法人建設コンサルタンツ協会誌記事「生物多様性がひらく世界」も、ぜひご一読ください。
http://www.jcca.or.jp/kaishi/249/249_toku8.pdf
無料ダウンロード等関連情報
- 無料ダウンロード:本多著作:震災復興ルポタージュ「未来をつなぐ人間物語」
- 無料ダウンロード:本多著作:「創資源物語~凡人による非凡なる挑戦~」
- 本多清のいまさら聞けない、「企業と生物多様性」コラム一覧
- アミタと高島市のコラボレーション「たかしま生きもの田んぼ米」
- アミタへのご依頼・ご相談
執筆者プロフィール

本多 清(ほんだ きよし)
株式会社アミタ持続可能経済研究所
主任研究員
環境ジャーナリスト(ペンネーム/多田実)を経て現職。自然再生事業、農林水産業の持続的展開、野生動物の保全等を専門とする。外来生物法の施行検討作業への参画や、CSR活動支援、生物多様性保全型農業、稀少生物の保全に関する調査・技術支援・コンサルティング等の実績を持つ。著書に『境界線上の動物たち』(小学館)