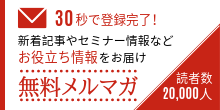コラム
いまさら聞けない「企業と生物多様性」(その4)-ローカル性こそが「ものがたり」の源泉本多清のいまさら聞けない、「企業と生物多様性」

前回、生物多様性の取り組みにおいては「数値よりもプロセスが重要」であり、可視化すべきものはプロセスすなわち「ものがたり」である、とご説明しました。では、どうすれば市場や社会から共感を得られる「魅力的なものがたり」を構築し、発信することができるのかを考えてみましょう。
生物多様性とローカル性
「御社のグローバルな活動に惹かれまして・・・」「うち国内企業なんですけど」。
就活の面接コントではお約束の台詞ですが、生物多様性の取り組みはグローバルとローカルのどちらでも重要になってきます。グローバルな面では主に調達ラインにおけるテーマや課題であり、ローカルな面では土地利用型、つまり工場や事業所等の拠点におけるものになります。
グローバル、すなわち調達ラインにおける生物多様性への配慮なくして、最終的な製品や商品の機能のみで「エコ」をうたい文句にしても、もはや社会の共感を得られないことは言うまでもありません。いくら消費電力の少ない電化製品であっても、調達ラインにおいて環境破壊や生物多様性の劣化を招いていては評価の対象になりえないわけです。もちろん、ローカル、つまり製造過程や拠点開発においても同様のことが言えます。
しかし、企業の活動がグローバルであろうとローカルであろうと、生物多様性における課題は常に「その影響が及ぶ現場」にあります。木材調達先のマレーシアの森林であろうと、地下資源を調達するアフリカの鉱山であろうと、従業員が働く工場周辺の地域であろうと「その地域の歴史で育まれてきた様々な生きものたち」と無関係でいることはありえません。ですから、つまるところはローカル(それぞれの現場)な視点と活動が、生物多様性における取り組みの中心にならざるをえないわけです。
今日、私たちの経済活動のために世界のどこかで切り倒される「一本の木」と、その木に日々の糧や暮らしの場を得ていた様々な生きものたちに想いをはせ、影響への対策を考えることはもちろん重要です。しかし、そうした視点を持つためには「足元の自然」を読み解く経験と知識が不可欠です。
第2回コラムで述べたとおり、生物多様性とは「それぞれの地域の歴史の中で育まれてきた様々な生きものたちが、互いに関わりあいながら暮らしている状態を表わす概念」であり、その「生きもの」の中には私たち人間も含まれます。つまり生物多様性とは「個々の地域における生きものたち(住民を含む)が織りなすローカルな物語の価値」そのものであるといえます。
このような視点に立つと、自社の工場や事業所のある地域の生物多様性を読み解き、そこに対する課題解決の行動をはじめることが、世界的な視野で生物多様性に取り組む上での大切な一歩、ということがご理解いただけるのではないかと思います。
地域の「ものがたり」を読み解く力
地域の自然の中で寄り添い、折り合いをつけながら生きてきた「人々と自然の共生の歴史」が築き上げた文化や風土。いうなれば「おらが村の自慢」こそが、生物多様性において企業がもっとも重視するべきテーマのひとつであると思います。
(※このような個々のローカル性の重視という概念が、ビジネスにおいては「強み(特色)の見極め」「差別化」さらには「顧客の囲い込み」というマーケティング戦略にも結びつきます。同時に、生物多様性における企業の姿勢を社会に示すツールにもなりえます。)
たとえば、みなさんの工場や事業所が建設される前、その地域にどのような風景が広がり、どのような生きものたちが暮らしていたか。また、その地域でどのような文化が育まれてきたか、考えたことはあるでしょうか?企業は本来、施設が立地する地域の環境や社会と無関係に存続することはできないのです。今までほとんど意識してこなかった、という方は、ぜひ「意識」してみてください。
そうは言っても、ただ「考えてみた」ところでなかなか具体的なイメージは思い浮かばないと思います。これは何も企業に限ったことではありません。現在は、その地域に暮らしている(企業外の)住民の多くにとってさえも、本来その地域が育んできた「ふるさとの景色や文化」「生きものたちのとの関り」というものが意識されにくくなっています。じつは、このことこそが近年の「生物多様性の危機」の背景といえるのです。生物多様性の取組みを通じて、これらの「意識の断絶」をもう一度結びなおすこと。それが、企業が社会に果たしうる大きな役割でもあるのです。
生物多様性の危機が今ほど深刻になる以前の時代は、営み(生産)と暮らし(消費)の場はほぼ一体化しているか、少なくとも現代よりはずっと近い距離関係にありました。とくに里山や田園の環境では、営みと暮らしは不可分の関係にあり、地域の自然資源(生態系サービス)に対する依存度合は現代よりもはるかに高く、その関係性も複雑でした。「○○の花が咲いたら(●●の鳥が鳴いたら、等々)、この農作業をする」というような具合に、自然からのメッセージを読み解かなくては生活が成立しないところが大きかったのです。
しかし、社会情勢の変化によって生産効率の向上が至上命題になると、ありとあらゆる環境が「生産効率の向上」という価値観のみで判断されるようになりました。「最大の生産効率をあげるための技術」が進む一方で「効率性の低いセクションは放棄(廃棄)」せざるをえなくなったのです。そうしなければ市場競争に負けてしまうわけですから選択の余地はありません。地球上の生物多様性が破壊もしくは劣化してきた背景には、こうした大量生産、大量消費、大量廃棄の市場経済システムが成長してきたことがあります。
さらに、このことの背景には生産地と消費地の分離が挙げられます。生産地では消費者の顔を知らず、消費者は生産地の風景を知りません。お互いに知らないもの同士がひたすら生産し、ひたすら消費するわけですから、その過程でどのようなことが起きているかなどを知る由もありませんし、伝える術もありません。伝える術がなければ、地域の環境でどんな変化が起きているかを感じ取る能力も失われていきます。その結果「ちょっと前まであんなにたくさんいたメダカが(ホタルが、カエルが)、いつの間にかいなくなった」という地域が続出することになりました。
いま「地域の歴史に育まれた様々な生きものたちと人の営みが織りなしていた物語」を語れるのは、かなりのご高齢となったお年寄りか、幸いにも記録資料が残されていた場合の研究者ぐらいではないでしょうか。
このように、忘れ去られようとしている地域の自然と人々の関わり方(即ち地域固有の文化)を、「その地域らしさを表わす公共財」として住民の誇りと共に見直し、守り育み、あるいは再生していくこと。これが、企業が生物多様性において取り組むべき社会責任の極めて重要な要素であると思います。
※本コラムを執筆した本多主任研究員が生物多様性とビジネスチャンスについて寄稿した一般社団法人建設コンサルタンツ協会誌記事「生物多様性がひらく世界」も、ぜひご一読ください。
http://www.jcca.or.jp/kaishi/249/249_toku8.pdf
無料ダウンロード等関連情報
- 無料ダウンロード:本多著作:震災復興ルポタージュ「未来をつなぐ人間物語」
- 無料ダウンロード:本多著作:「創資源物語~凡人による非凡なる挑戦~」
- 本多清のいまさら聞けない「企業と生物多様性」コラム一覧
- アミタと高島市のコラボレーション「たかしま生きもの田んぼ米」
- アミタへのご依頼・ご相談
執筆者プロフィール

本多 清(ほんだ きよし)
株式会社アミタ持続可能経済研究所
主任研究員
環境ジャーナリスト(ペンネーム/多田実)を経て現職。自然再生事業、農林水産業の持続的展開、野生動物の保全等を専門とする。外来生物法の施行検討作業への参画や、CSR活動支援、生物多様性保全型農業、稀少生物の保全に関する調査・技術支援・コンサルティング等の実績を持つ。著書に『境界線上の動物たち』(小学館)
おすすめ情報
お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?
- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい
- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?
- アミタのサービスを詳しく知りたい
アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード
資料やセミナー動画をご用意しております。
是非、ご覧ください。