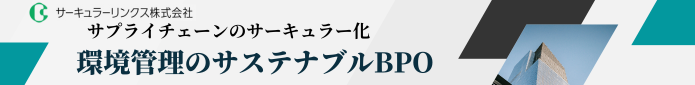Q&A
食品リサイクル法を分かりやすく解説! その対象範囲と定期報告の概要まで
 Some rights reserved by szczel
Some rights reserved by szczel
本来食べられるのに捨てられる「食品ロス」の量は年間523万tのうち、食品産業から発生する事業系食品ロスは279万t(53%)、一般家庭から発生する家庭系食品ロスは244万t(47%)です※2021年実績。今回は、事業系食品ロスの減量化、再生利用を促進する「食品リサイクル法」について、その対象範囲から定期報告までお伝えします。
※本記事は2022年に執筆した記事を加筆、修正しています。
関連記事 コラム:企業・地域を変える!?「ゼロ・ウェイスト」の可能性
|
目次 |
食品リサイクル法とは
- 趣旨と方針について
食品リサイクル法(以下、食リ法)とは、食品産業に対して食品循環資源の再生利用等を促進するための法律です。食品関連事業者(製造、卸売、外食等)は、食品の売れ残りや製造過程で発生する食品廃棄物を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用することが求められています。
食リ法が定める再生利用等の優先順位は、まず食品廃棄物そのものの「発生を抑制」することが推奨されており、次に再資源化できるものは飼料や肥料、メタン化などへの「再生利用」を行うことです。再生利用が難しい場合は「熱回収」を行い、さらに、これらの方法でも難しい場合は脱水、乾燥などで「減量」したうえで、適正に処理がしやすいように加工することとされています。
- これまでの改正の流れ
2001年に施行された食リ法は一定の効果をあげたものの、食品産業の「川下」に位置する小売業などの食品関連事業者の取り組みに関しては効果が薄かったということから、食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等の取り組みの円滑化措置を講ずるとし、2007年に改正されました。
関連記事:2007年12月に改正された食品リサイクル法で新たに加わった「熱回収」とは、どういうものですか?
さらに2016年1月に発生した食品廃棄物の横流し事件を受け、環境省は対策の強化を検討した結果、2017年1月26日に判断基準省令等の改正と食品関連事業者向けガイドラインを公表しました。
関連記事:食品廃棄物の横流し・不正転売防止に向けた食品リサイクル法の判断基準省令等の改正について教えてください。
そして、食品の再生利用だけでなく、2050年までのカーボンニュートラル達成や2030年度削減目標の達成、つまりエネルギーとしての利用を推進するため、2024年に食品リサイクル法の一部が改正されることが決まりました。
以下が、今回改正された主要な2つのポイントです。
- 登録再生利用事業者制度の改正
食品を再利用するための事業者登録について、過去1年間に特定の肥料や飼料を製造・販売した実績がない場合でも、その実績を保証できるのであれば、前もって登録できるようになりました。 - 食品循環資源の再利用に関する基本方針改正
・エネルギー利用の推進を基本方針に追加
2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする「カーボンニュートラル」や、2030年の削減目標を達成するため、食品の再利用において、エネルギー利用を推進することが追記されました。
・焼却・埋立ての削減目標を設定
未利用の食品廃棄物を意識し、さらに再生利用を推進するために、「焼却・埋立ての削減目標」が参考値として設けられました。
・社会全体で食品廃棄物削減に取り組む重要性について強調
食品関連事業者だけでなく、社会全体で食品廃棄物削減に取り組むことが、持続可能な社会の構築には重要であると強調されました。
食品リサイクル法の対象とは
- 対象となる事業者は?
それでは食リ法に規定される事業者とは誰を指すのでしょうか。
食リ法において事業者の定義は次に掲げる者をいいます。
|
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第2条 4項 一 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者 |
つまり、食品を扱う事業者全般がその対象となります。
では、食品関連事業者は具体的には何に取り組めばよいのでしょうか。
- 食品関連事業者が取り組むべきこと
食品関連事業者が取り組むべきこととしてガイドラインが発表されていますので以下、ご紹介します。
▼食品関連事業者向けガイドラインの具体例・対策
| 食品廃棄物等の処理委託時・契約時における対策例 |
|
|
食品廃棄物等の引渡し時における対策例 |
|
| 食品廃棄物等の処理終了時における対策例 |
|
- 義務と罰則
次に、食リ法の義務や罰則についてご紹介します。 食リ法をみると、2009年から食品廃棄物等多量発生事業者(食品廃棄物等の前年度の発生量が100t以上の食品関連事業者)は、毎年6月末までに、主務大臣に対し食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられています。
罰則については、食品廃棄物等多量発生事業者の再生利用等が不十分な場合、主務大臣により勧告、公表、命令されます。また、命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
- 定期報告について
では、食品廃棄物等多量発生事業者の義務となっている定期報告はどのように行えばいいのでしょう。以下、基礎的な情報をまとめました。
・報告する事項
主に廃棄物等の発生量、発生抑制の実施量、再生利用の実施量と実施率など、17の報告事項があります。
・報告書の様式
農林水産省が毎年定期報告書をホームページで掲載しています。作成にあたっての参考資料等も同ページに掲載されているので、ご参照ください。
農林水産省ホームページ:食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等_令和2年度実績報告書
・報告書の提出方法
2020年度より、定期報告は、
- 「農林水産省共通申請サービス」のファイルアップロード機能による報告
- 電子メールへのファイル添付による報告
のいずれかを基本とすることとなりました。
なお、これらの電子申請が難しい場合、主たる事務所(本社等)の所在地を管轄する地方農政局に紙の報告書を提出するという方法もあります。詳しくは、農林水産省の「食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等」を参照ください。
農林水産省ホームページ:食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等
・その他
定期報告についてより詳しく知りたい場合は、関東農政局が主催している食品関連事業向けの定期報告説明会が毎年web説明会を実施していますので、その際の資料等をご参照ください。
関東農政局ホームページ:令和6年度定期報告に関するWeb説明会の資料について
▼関連記事
震災によって発生した食品廃棄物も、食リ法の定期報告に含める必要はありますか?
- 対象となる食品とは
次に食リ法において「食品廃棄物等」とは、何を指すのでしょうか。
食リ法においての定義は、次に掲げるものを指します。
|
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第2条 2項 一 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの |
食リ法の食品廃棄物とは、飲食店で発生した食べ残しだけでなく、食品メーカーやスーパー等各サプライチェーンで発生した食品廃棄物も含んでいます。
- 再生利用方法
食品廃棄物はどのように再生利用されるのでしょうか。
食リ法で定められた再生利用方法には、以下のようなリサイクル方法が挙げられています。
▼食リ法で定められている再生利用方法
| 飼料化 |
脱水や乾燥によって製造する乾燥方式、乳酸発酵させて製造し牛用飼料となるサイレージ方式、液状に加工し製造し豚用飼料となるリキッド方式があります。飼料化は、飼料自給率の向上にも寄与するため、優先的に行うことが推奨されています。食品廃棄物等多量発生事業者における再生利用の実施量内訳では、飼料化が約9,000tと最も多いです。 |
| 肥料化 |
肥料化は、他のリサイクル手法と比べて、初期投資が少なく技術的なハードルが低いことから比較的始めやすい再生利用方法です。 |
| きのこ菌床 | きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地として活用する再生利用方法です。 |
| メタン化 | メタン化とは、食品廃棄物などの動植物に由来する有機物をメタン発酵し、メタンガス(バイオガス)を生成することです。生成されたメタンガスは、電気や熱などのエネルギー源として利用されます。食品卸売業や外食産業が扱う食品残さは異物の分別が困難なものもありますが、メタン化は比較的分別が粗くても対応が可能な場合もあります。 |
| エタノール、炭化 | 食リ法で認められている再生利用方法ですが、日本での再生利用実施量は小量です。 |
| 油脂化及び油脂製品化 | 油脂化及び油脂製品化については、多くが飼料添加用油脂や脂肪酸原料として有効活用が可能です。 その他、廃食用油をバイオディーゼル燃料として有効活用する取組が進んでいます。 |
なお、これらの再生利用方法のうち今回の基本方針の改正・エネルギー利用の推進に関連するのは、多くがエネルギー利用にあたる「メタン化」「エタノール化」「炭化」「油脂化及び油脂製品化」を指します。
その他再生利用方法別の特徴については、環境省ホームページ:政策分野・行政活動 審議会・委員会等資料よりをご参照ください。
また食リ法において熱回収は、まず飼料化や肥料化など他の再生利用方法を検討すべきとし、これらが困難な場合、熱回収を行うという位置づけになっています。食リ法および、熱回収省令で定められた一定の要件を満たした事業者のみが、再生利用方法として熱回収を行ったと認められます。詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
環境省ホームページ:食品リサイクル関連 熱回収施設
食品ロスの現状と環境
- 食品リサイクル法の目標と達成状況
2019年7月12日に公表されている基本方針では、食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業に対して2024年度までに、下記の目標値を達成するよう定められています。
| 業種 | 令和4年 | (参考)令和元年 | 目標値 |
| 食品産業計 | 89% | 85% | - |
| 食品製造業 | 97% | 96% | 95% |
| 食品卸売業 | 62% | 64% | 75% |
| 食品小売業 | 61% | 51% | 60% |
| 外食産業 | 32% | 32% | 50% |
出典:農林水産省
では、目標値と現状の実施率にはどれぐらい差があるのでしょうか。2019年(令和元年)と現在公開されている最新版2022年(令和4年)時点での達成状況とを比較してみましょう。食品産業全体の再生利用等実施率は89%で、これを業種別にみると、食品製造業は97%、食品卸売業は62%、食品小売業は61%、外食産業は32%で、卸売業以外は全て達成率は上昇していました。2022時点で、2024年目標未達であった卸売業と外食産業が、その後再生利用等実施率を引き上げられているかどうかが気になるところです。
- 排出事業者としての環境への取り組み
持続可能な食糧生産・供給が求められる時代に、食品関連事業者にはより一層厳しい食品廃棄物の発生抑制、さらなる再生利用等実施率の向上が求められています。
これらを達成するには業界全体の意識改革はもちろんですが、各食品関連事業者が自社の食品廃棄物の管理状況をしっかり把握しておく必要があります。また2024年の改正では事業者以外、つまり私たち一般消費者への食品リサイクルへの取り組み推進にも言及しています。社会全体で食品循環資源の再生利用向上とともに、サーキュラーエコノミーの推進を進めていきましょう。
関連情報
全ての廃棄物情報を見える化する「LinX Management(リンクスマネジメント)」と、廃棄物管理から環境管理業務までのオペレーションを担うアウトソーシング「LicnX BESTWAY(リンクスベストウェイ)」を提供する、アミタグループの新会社・サーキュラーリンクス株式会社は、企業のサーキュラーエコノミー推進を支援します!
おすすめ情報
お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?
- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい
- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?
- アミタのサービスを詳しく知りたい
アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード
資料やセミナー動画をご用意しております。
是非、ご覧ください。